デザインは「飾り」ではない
デザインと聞くと「かっこいい」「おしゃれ」「かわいい」といった見た目の印象に注目されがちですが、本当に大切なのは「意図=目的」です。
誰のために?何のために?どんな行動を起こしてもらいたいのか?
それを明確にしないまま進めると、どれだけ見た目が整っていても「伝わらない」「反応がない」デザインになってしまいます。
見た目より、まず「意図」を言葉にする
どんな目的があるのかをはっきりさせる
- 商品を買ってもらう
- イベントに参加してもらう
- ブランドの世界観を伝える
など、デザインには必ず何かしらのゴール(意図)があります。
これが曖昧なまま「かっこよくして」と依頼すると、見た目は整っていても、ゴールに届かないことも少なくありません。
意図があるから、選べる
「なぜこの色を選ぶのか」「なぜこのフォントにするのか」――それは見た目の好みではなく、意図に基づいて選ぶべきです。
たとえば、信頼感を出したいなら「青」、子ども向けにしたいなら「明るい色+丸ゴシック」など、意味のある選択ができるのがプロのデザインです。
「目的から考える」デザインの流れ
1. 誰に届けたいか(ターゲット)を考える
誰に向けて作るのかによって、言葉のトーンも色も構成も変わります。
- 学生向け → カジュアルで動きのあるレイアウト
- 高齢者向け → 大きな文字と落ち着いた配色
- 女性向け → 柔らかさ・共感を大切にした雰囲気
2. 何を伝えたいか(メッセージ)を絞る
情報をたくさん盛り込むのではなく、何を一番伝えたいのかを絞ることが、デザインの軸になります。
- 商品の魅力
- 期間限定の訴求
- 初心者でも安心できる内容
目的によって強調ポイントが変わります。
3. どんな行動をしてほしいか(アクション)を決める
「問い合わせしてほしい」「QRを読み取ってほしい」「SNSでシェアしてほしい」など、相手にしてほしい行動を明確にして、それがしやすいようにデザインします。
「おしゃれ」だけでは届かない
よくある失敗例として、次のようなものがあります:
- 見た目がきれいでも、何を伝えたいのかわからない
- 情報が多すぎてどこを見ればいいのか迷う
- 自分では満足しているが、誰にも届かない
これはすべて、「意図」より「おしゃれ」が優先されてしまった状態です。
まとめ:「伝える」ためのデザインを
デザインの目的は「伝えること」「動かしてもらうこと」です。
見た目は大事ですが、それは意図をカタチにする手段のひとつ。
デザインの力を最大限に発揮するには、まず“何のために作るのか”という目的をクリアにすることが第一歩です。

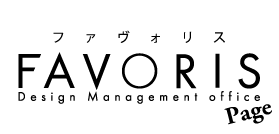



コメント